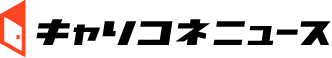スマートに、でも、熱く。アンカー・ジャパンのリテール営業最前線

2010年に中国で創業したAnkerグループ。その中で2番目に大きな市場である日本のリテール事業を担うのが大滝 浩司です。あらゆるステークホルダーに対して常に真摯な姿勢を貫く、彼のスタイルの源流をたどります。【talentbookで読む】
ITの可能性を肌で感じ、ビジネスの世界に飛び込んだ
2000年代前半、日本のビジネスシーンでIT産業が盛り上がりを見せ始めていました。
ノートパソコンの普及が進むも、スマートフォンもまだ存在しなかったころのこと。インターネットビジネスは社会を大きく変革させる──。そんな予感が、徐々に現実化し始めていた時代でした。
大滝も、学生時代にITベンチャーでインターンを経験し、新時代のビジネスに興味を抱いていたひとりでした。
大滝 「 ITには全然詳しくなかったので『インターネット検索って便利な機能だ!』『検索上位に表示されているのは実は広告なんだ!』と驚きの連続で……。インターンを通じてユーザーでは知りえない裏側を垣間見ることができ、ビジネスとして興味を抱くようになりました」
就職活動でもIT業界に軸足を置きつつ、もうひとつの軸を求めていた大滝。
そこで彼が選択したのがマーケティングリサーチという仕事でした。
大滝 「 ITを活用してお客様の声を集め、クライアントに届ける。そんなビジネスモデルに惹かれ、新卒でインターネットリサーチ会社に入社しました。新規業界を開拓する営業担当として、 IT企業や不動産企業などに営業活動を行っていました」
当初手がけていたのは、出稿した広告の効果測定調査。調査のしくみそのものは他社と大きく差別化できるわけではありませんでしたが、その中で大滝が特に注力したのは、クライアントの課題に対してさまざまな提案をすることでした。足しげく通いつめ、顧客に入り込み、ヒアリングを重ねて関係性を深めながら課題解決を提案するスタイルを築いていきました。
大滝 「いろいろなお客様と出会いました。その中で自分にとって理想的だったのは、対等なビジネスパートナーとして認めていただけたとき。同じ目線で課題を見つめ、一緒に歩んでいけると感じられると、仕事のやりがいは大きかったですね」
入社から5年ほどが経ったころ、大きなやりがいを感じる一方で、大滝の胸には「次のステージに進みたい」という想いが芽生え始めます。そんな彼が選んだ次のステージ──。
それは、海外でのビジネスでした。
思考も文化も異なる中国で得たスピード感覚と多様性
2013年、大滝は中国・上海に設立された現地法人にて、立ち上げ責任者と入れ替わるかたちで、現地での事業責任者のポジションを任されました。
大滝 「学生のころは海外志向なんて全然なかったのですが、社会人としてキャリアを積んでいく中で、徐々に目線が海外へと向いていきました。世界最大の人口、広い国土の中での多様な文化や価値観に惹かれ、中国に行くことを決めました」
現地にいる日本人スタッフは、大滝を含めてふたりだけ。
スタッフの採用やマネジメント、現地の日本法人の経営者を相手にした商談など、国内でビジネスを行っていたころと比べ、一段高いレイヤーでの業務を担うことになりました。
「日本とは何もかもが違った」と大滝は話します。
大滝 「まず感じた日本との違いは、圧倒的なスピード感。決裁ひとつをとっても、ものすごいスピードで進みますし、気づいたら空地にビルが建っているなんて日常茶飯事でした。そのスピード感は、新しいワクワク感でもありました。
あと、中国人スタッフは考え方がとにかくシンプル。やると決めたら、ひたすら集中してやりきる意識と行動力がすばらしかった。残業もしません。シンプルな思考だから、ためらいも忖度もしない。良し悪しではなく、単純に仕事に対する考え方の違いを感じました」
ローカルスタッフを統べるには、こうした違いの理解と受容が欠かせません。
大滝はすぐに「日本の常識にあてはめようとしてもダメだ」と気づきます。
大滝 「自分が誰かをコントロールするのだという感覚はすぐに捨てました。コントロールなんてできないし、必要以上の期待を持ってしまうと、満たせなかったときに良くない感情が生まれますから。依頼した仕事を果たせなかったら、その理由を一緒に考えて改善すればいいんです」
一方で、現場の感覚にそぐわない指示や要求に対しては、徹底的に戦いました。
大滝 「たとえば、現場の実情が加味されていない売上目標に『がんばります』と言ってしまうと、無謀な数字を追うことになり、スタッフのモチベーションが下がります。できないことにはできないと言い、できる提案で交渉や調整をする、それがマネジメントの役割だと痛感しました」
赴任から3年が経過したころ、再び大滝に転機が訪れます。それは、突然の帰国辞令。日本に戻り、海外駐在の経験を生かした新たなポジションでしたが、中国でスピード感のあるビジネスを経験した大滝にとっては、さらなるステージアップとは感じられませんでした。そこで、「新天地を探そう」と決意したのです。
アンカー・ジャパンに入って、営業という仕事は180度変化した

なぜ、このひとたちがこの会社にいるんだろう──?
アンカー・ジャパンの井戸や猿渡らと面談を行った大滝の第一印象は、そんな疑問から始まりました。
大滝 「たとえばマーケティングリサーチなら、リサーチャーという分析のプロが集っています。いわゆる “その道のプロ ”ですね。
でも、アンカー・ジャパンはメーカーなのに、経営陣のバックグラウンドは投資銀行や戦略コンサルなんです。純粋な疑問と、おもしろそうな会社だなと感じたのを覚えています」
アンカー・ジャパンはスマートフォンの普及にともなうモバイル周辺機器市場の拡大を確信していました。またAnkerグループとしては、オーディオ製品や家電製品など、チャージング関連製品以外の領域にも事業進出を果たしており、多様なカテゴリーの製品開発力の高さも感じた、と大滝は振り返ります。
さらには、Ankerグループは中国が本国。経験上、スピーディな事業展開を期待できたことも魅力に映りました。
そして2016年、大滝はアンカー・ジャパンに入社します。
大滝 「クライアントにサービス提案をしてきた立場から一転、形あるプロダクトを一般消費者に販売することになったわけです。数百以上の自社製品を覚えたり、これまでの仕事とは異なり、“顔の見えないお客様 ”に販売しなければならない難しさに直面しました」
大滝の担当はオフライン販路(リテールビジネスをメインとしたクライアント)における営業活動。家電量販店などにAnker製品を置いてもらうための商談を行っていました。
大滝 「商習慣も違えば、販売管理費の使い方も違う。卸として商社もいる。直取引でクライアントのもとに通うのとはまったく別物の営業活動です」
日々コミュニケーションを取る取引先企業との結びつきも、前職とは違うものになった、と大滝は言います。
大滝 「モバイルバッテリーや USB急速充電器という製品や電気関連の知識など、ゼロからアドバイスするような説明が必要になるシーンが多いです。
でも、それが Ankerのユーザーのインサイトに通じる部分もあって、たとえユーザーに直接販売するわけでなくとも、そういったコミュニケーションの重要性は変わらず大切なんだと実感しています」
クライアントワークから事業会社へ。
マーケティングリサーチからモバイルバッテリーなどを展開するメーカーへ。
属する場所や販売する製品が変わっても、“変わらないもの”が実は他にもありました。
最後はやっぱり“ひと対ひと”。顔の見えるコミュニケーションを大切に

Ankerは、中国で創業してすぐにアメリカ市場に参入。そこで確固たるブランドの地位を築きながら、積極的に全世界へと事業展開してきました。
それだけに、ブランドへの信頼や確たる実績は日本市場でも圧倒的な武器になる、と大滝は断言します。
大滝 「安全性や信頼感も、 Ankerが誇る大きな価値と言えます。さらにより幅広い製品にも展開するなど、事業成長の可能性も強みですね。
量販店などは、製品を手に取っていただける貴重なタッチポイント。オンライン( Eコマースでの販売)とは一線を画する店頭販売ならではの良さを生かし、いかに Ankerの魅力を伝えるか。日々、試行錯誤しています」
そうした狙いのもと、2019年現在リテール事業は大滝を含めたセールスや営業事務、サプライチェーン担当、インターン、本国の担当者などが連携し、組織だった活動を実現できています。
対ひとのコミュニケーションを重視する姿勢は、今なおぶれることはありません。
大滝 「弊社はコミュニケーションのスピードが非常に速いのが特徴です。立ち話やチャットのやり取りだけで意志決定していける柔軟さとスピード感は、とても良い社風です。
一方で、ひと対ひとのコミュニケーションもなくしたくはないのです。システマチックな簡略化はビジネスのスピードアップに貢献しますが、相手の雰囲気が伝わるやり取りや共感も同様に大切。
最終的にはお互いに顔を突き合わせて、『一緒にがんばろう』という雰囲気が好きなんです」
理想は、どんなステークホルダーとも“フラットな関係性”を築けること。たとえ取引先や上司であろうとも真摯な姿勢で臨むコミュニケーションを、大滝は常に意識し行動しています。
それこそが、お互いにとって良い結果を導くのだと信じて──。
アンカー・ジャパンの事業成長は、まだまだ道半ば。
「当社の存在価値をもっと世の中に届けていくために、貢献し続けたい」という展望の実現に向けて、スマートに、でもひとの温度感は失うことなく、大滝のチャレンジは加速し続けていきます。