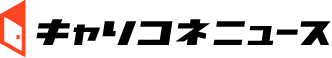潜入取材ふたたび!“ユニクロ”横田増生氏が「アマゾン帝国」の内側で見たもの

アマゾン市川フルフィルメントセンター(千葉)の前に立つ横田増生氏
身元を隠すために離婚、改名までした『ユニクロ潜入一年』(文藝春秋刊)で一躍脚光を浴びたジャーナリスト、横田増生氏。その取材手法は、15年前から変わらず続いていたものだった。現場に入り込み、隠された事実を明かす。相手が秘密主義を貫くほど、隠したいところに入り込む。ジャーナリスト本来の姿を愚直なまでに追求する横田氏に、スタイルの源流と最新刊『潜入ルポ amazon帝国』(小学館)について聞いた。
1日2万歩以上「初日で足にマメができた」
――ユニクロ本で有名になった横田さんですが、その後も潜入取材を続けています。
横田 次に出した『仁義なき宅配』(小学館文庫)では、宅配ドライバーの助手や物流センターのアルバイトとして潜入取材をしました。ユニクロほど目立ちませんでしたが、同じぐらい売れましたね。
――最初の潜入はどこですか。
横田 15年前のアマゾンです(朝日文庫『潜入ルポ アマゾン・ドット・コム』として、マーケットプレイスで入手可能)。2004年当時、アマゾンの物流センターは市川塩浜にしかありませんでした。扱う商品も書籍だけで、もっと海側の奥の方にあって規模も小さかった。
ここのピッキング(倉庫内をまわって棚から商品を集める作業)のアルバイト求人を見て、単純に自宅から近かったですし、取材しながらお金がもらえれば他のところの取材もできるなと。潜入取材は賭けの部分が大きいんですが、入ってみたら殺伐としていて、これは面白いと思いました。
――今回はアマゾンで最も大きな小田原のフルフィルメントセンターに潜入しています。
横田 本にも書きましたが「とてつもなく大きくなったな」というのが率直な感想です。「The Everything Store(あらゆるモノを扱う店)」をうたい、たこ焼きの粉からスマホの充電器まで、アマゾンにないものを探すのが難しいくらい。以前から人を人と思わず、駒のように使うところがありましたが、それがより徹底されていました。
――作業用のハンディ端末に「次のピッキングまであと何秒」と表示されるところなど、合理的であるとともに、余裕がなく疲弊する人も多いだろうと思いました。
横田 朝礼で目標達成のプレッシャーをかけられて、午前9時から午後5時まで2万5000歩以上、距離にして20キロ超は歩くわけです。それで時給1000円以下ですからね。儲かってるんだからもっと払えよ、と思ってしまいます。
――ピッキング作業中に亡くなっている人が、小田原だけで5年間で少なくとも5人はいたというところが衝撃でした。
横田 労働時間が過労死基準を超えているわけではありませんが、かなりの重労働です。これはどの国でも同じで、イギリスで潜入取材をした若いジャーナリストもずいぶん痩せたと言っていました。僕も初日で足にマメができました。
業務中に亡くなっても、遺族にわたるのは派遣会社から香典3万円だけ。アルバイトにアルバイトを管理させ、アマゾンはアルファベットでしか名前を知らない。派遣会社が徹底的に忖度し、「アマゾン様」に都合のいい方法を採っています。
実践的だった米大学院の教え方

横田増生(よこた・ますお)1965年福岡県生まれ。関西学院大学文学部英文科卒業。予備校講師を務めた後、アメリカのアイオワ大学大学院でジャーナリズムを学ぶ。物流業界紙の編集長を務め、フリージャーナリストに。
――横田さんは、いつジャーナリストを志したのですか。
横田 大学時代に読んだノンフィクションの本が面白かったんです。当時は、本多勝一(朝日新聞)や近藤紘一(産経新聞)、黒田清(読売新聞)といった人たちがノンフィクションを書いていて、新聞社で修業するのも悪くないなと。
でも、新聞社は試験が難しかったし、勉強もあまりしなかったから入れなかった。それで、アメリカには大学院でジャーナリズムを教えるところがあるなと思って、予備校講師で渡航費用を貯め、奨学金をもらいながらアイオア大学の大学院に行きました。
――アメリカの大学院では、どんな教え方をするんですか。
横田 先生はみんなジャーナリスト出身で、AP通信やローリング・ストーンズ誌、大手地元紙の元記者。彼らが編集長で、学生が記者となってテーマを一緒に考えて書きます。それを地元紙でも学生新聞でも、どこかに売り込んで活字になったら評価が上乗せされる。職業訓練に近い実践的な教え方でした。
ちなみに、学生新聞といってもかなり本格的で、ブランケット判(普通の新聞紙の大きさ)で12ページの新聞を週5日発行していました。大学院に通っている間は、そこの編集部でも働いていました。
――先生が原稿に赤字を入れてくれるんですか。
横田 ええ。よく言われたのは「とにかく具体的に書け」ということ。描写を具体的にとか。キーとなる質問を何回聞いたか、ということも確認されましたね。人は答えるうちに言い方も変わるから、聞き方を変えて何回も聞くように、と言われました。
――アメリカ時代に潜入取材の経験はありましたか。
横田 そういえば大学院生のとき、同級生がマンホールの中で暮らす人のルポを書いていました。実際に一緒にマンホールの中に住んで。それを読んで面白いなと思って、僕も生活困窮者向けの教会でのフリーランチを食べに集まる人々の取材を1か月してみたんです。でも若いアジア人なんて周囲にいないから浮いてしまって、そのときはうまくいきませんでした。
帰国して物流の業界紙に入り、編集長をしていたころは、新入部員に物流会社の「同乗取材」をさせていました。でも業界紙というのは読者も取材先も広告主も同じ業界ですから、ネガティブなことは書けないし、タブーもたくさんある。ぎりぎりでどこまで書けるかという挑戦をしていて、いろいろ怒鳴り込まれたりもしたんですが(笑)、やはり厳しいことを書くには限界がありましたね。
「事実」を知った上で使った方がいい

アマゾンジャパン目黒本社に掲げられた「多様性と包容」のスローガン(横田氏提供)
――今回も倉庫だけでなく、宅配ドライバーに同乗したり、AWS(アマゾンのクラウドサービス)セミナーを聴講したりと、いろいろ潜入しています。
横田 AWSの潜入取材は1日7万円のセミナーを20人で受けました。ひとつも理解できませんでしたが(笑)、このとき目黒本社の壁に「DIVERSITY & INCLUSIVITY(多様性と包容)」とか「EARTH’S MOST CUSTOMER-CENTRIC COMPANY(地球上で最も顧客を中心に置いた会社)」といったスローガンが掲げられていたのを見ました。
一方、小田原の倉庫の壁に貼られているのは「厳正に対処」とか「不審者」とか、「犯罪行為」とか「即退社」といった殺伐とした言葉ばかり。これじゃ多様性も包容もあったものではない。消費者中心主義の名のもとに、労働者が極限まで搾り取られている。本社で働く人たちは、そういう末端の労働環境を知らないのではないでしょうか。
――ネットからは「嫌なら辞めれば?」という声が来るかもしれません。
横田 でも、アマゾンが倉庫を置いている場所には、それ以外の仕事がないんですよね。数百人の雇用を生むアマゾンは地元の自治体から歓迎されるし、生きるためにぎりぎりの人たちが「困ったときのアマゾン頼み」で集まってくる。作業中の夫が命を落とした職場に、妻が働きに通っている。これは社会の問題ではありますが、アマゾンがそういう環境を利用しているといえます。
――ユニクロ本のときには「ここまでやらないとグローバル競争に勝てないんだ」という反論もありました。しかしアマゾンの場合、特にヨーロッパの動きと比較すると明確に問題があり、日本でも解決に向けた動きが必要と感じました。
横田 イギリスでは租税回避の問題について、国会議員が激しい怒りを表していました。ドイツでは労働組合が何度もストライキを打ち、会社は交渉のテーブルについていないものの、時給が少しずつ上がっています。でも日本は、政治家も労組も圧力をかけない。
特に日本の労働環境については、派遣会社の多重構造であるとか、始業をいつからカウントするかの手待ち時間といった細かな部分を含めて、労働法に詳しい人が会社と交渉する必要があります。日本の労組は、アマゾンの物流センターの労働者を組織できるのか、真価が問われるところです。
――しかしアマゾンのサービスを絶対に使うな、という呼びかけはいまさら難しいです。
横田 アマゾンは僕も散々使っていますし、消費者から見たら本当に便利な世の中になったと言えるでしょう。でもこれまでは、その中で働いている人たちがどういう環境に置かれているのか、取引先との間にどういう問題があるのか、その事実自体があまりにも知られていないというか、秘密裏にされてきた。
それを僕が取材して書いて、事実を提示して、どうですかと。知った上で使った方がいいんじゃないですか、ということです。それをどう判断するかは、読者次第ですが。