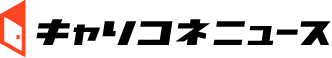ヨシキリザメを鑑賞しつつ、おいしく食べる! 水族館を異色のアイデアで盛り上げる商社マン
子どもからお年寄りまで幅広い年齢層が楽しめるレジャー施設として人気がある水族館。厳しい夏の盛りの帰省中、足を運ぶ人も多いことだろう。
2015年7月、仙台市に新しい水族館がオープンした。大手商社として初めて三井物産が開発した「仙台うみの杜水族館」だ。8月11日放送の「ガイアの夜明け」(テレビ東京)は、水族館事業に携わる社員に密着し、開発の裏側を紹介した。
三井物産が「水族館ビジネス」で復興を支援
なぜ商社が水族館事業なのか。その理由には、当然この地が震災の津波によって甚大な被害を受けた場所であることが関係している。今年4月に三井物産の社長に就任した安永竜夫氏は、会見でこう説明した。
「産業を起こすことが、商社の役割。ひとつの産業として、水族館ビジネスを行う。継続的に地域の活性化や雇用につながるビジネスを通じて、復興を支援したい」
オープン前の5月、宮城県で唯一の水族館である「マリンピア松島水族館」が88年の歴史を閉じた。うみの杜水族館には、松島水族館で展示していたすべての生き物を移動させ、飼育員も雇用し経験も受け継いでいる。
移動を見守るのは、三井物産・コンシューマーサービス事業本部の吉井新さん(37歳)だ。以前はアパレル業や不動産関係で世界中を飛び回っていたが、3年前から水族館事業に携わっている。被災地仙台で仕事をする特別な思いを、吉井さんはこう語った。
「海から気持ちが離れてしまう経験をしてきた人々に、あらためて東北の海の素晴らしさを感じてもらえる場にしていきたい」
最大の売りは、世界三大漁場のひとつ地元の三陸沖を再現した巨大な水槽だ。魚の種類が豊富で、マイワシの群れが銀色に光りながらうねるように泳ぐ。気仙沼は江戸時代からヨシキリザメがよく獲れ、フカヒレの商いで栄えてきた街だ。
「ヨシキリザメの解体ショー」が大盛況
新しい水族館は地元に愛される施設をめざして、展示のメインにヨシキリザメを考えていた。しかしこのサメは長期飼育が難しく、他の水族館でも飼育例がほとんどない。ノウハウなしの手探り状態だ。
展示にいたるまでには、横浜・八景島シーパラダイスの社員を展示責任者に迎えての奮闘があった。7月1日のオープン初日には7000人の来場者でにぎわったものの、ヨシキリザメの展示は間に合わなかった。捕まえてきても、大水槽の岩や壁にぶつかり死んでしまうのだ。
1か月後、新たに捕獲されたヨシキリザメは、サメがぶつからず泳げるようになるまでさまざまな配慮の下で飼育された。緩衝材を置いたり、岩にぶつからないようダイバーが潜って誘導したり。
家族連れで賑わう夏休み、水族館ではあるイベントが多くの来館者を集めて大盛況となった。それはなんと「ヨシキリザメの解体ショー」。近くの売店ではサメのフライ「シャーク&チップス」がよく売れていた。
かたわらでは、アイデアを出した吉井さんが笑顔で見守る。吉井さんは事前に水産加工会社に足を運び、ヨシキリザメの身の調理法や加工品を研究していた。食べ物として活かされているヨシキリザメを、より身近に感じてもらおうという狙いだ。
一歩引いて考える「自分がお客さんだったら」
オープンから1か月の来場者数は予想を大きく上回り22万8000人。8月に入りさらに勢いが増している。大水槽では美しい青色をしたヨシキリザメが悠然と目の前を横切る姿に子どもたちが大はしゃぎ。ある男性客は「生きてる姿は新鮮ですね」と感動していた。
ヨシキリザメの泳ぐ姿を眺め、それをおいしくいただくという発想が、このサメに人一倍思い入れを抱く吉井さんから出たことに複雑なものを感じた。しかし、見て食べるという感覚に訴えることは、結局一番手堅い戦略なのかもしれない。
「自分自身がお客さんだったら、どういうものがいいのか。そういうところを一歩引いて見ることも大事だとあらためて感じています。これで終わらずに次につなげていきたい」と吉井さんは、商社マンらしく商材を生かす術を懸命に考えていたのだろう。(ライター:okei)
あわせてよみたい:日本の漁港は「宝の山」