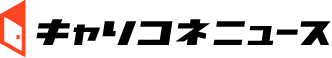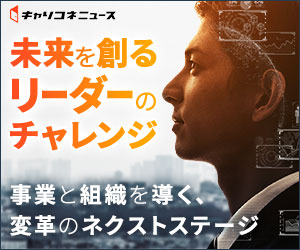高知県、シラスウナギの採捕期間延長で「絶滅させる気か」の声相次ぐ 担当者は「元々の漁期間が他県より短い」と妥当性主張

絶滅の阻止と、養殖業者や漁をする人の生活維持、両立させる方法はないものでしょうか
2月26日の高知新聞によると、「県しらすうなぎセンター」に集まったシラスウナギは約4.2キログラムと、前年同時期の約4%しかなかった。県の担当者は不漁の原因について「潮が後ろにずれているせいではないかと言う人もいるが特定できていない。個体数減少の影響があるかどうかも、県として明言はできない」と話す。今回の決定は
「高知県だけが不漁なら、養鰻業者も他県に行って買うことができる。しかし今年は全国的に不良なのでそういったこともできない。やむを得ない」
とこぼしていた。ウナギの絶滅が危惧されている状況は知っているというが、
「資源管理の重要性は認識している。ただ、高知県は他の都道府県より採捕期間が短いなど、資源管理は厳しい方だ。100日以上の採捕期間を設ける県もある中で、15日延長したとしても95日。他県より短い」
と、期間延長の妥当性も主張していた。シラスウナギの採捕は12月から4月の間で各都道府県が設定できるが、高知県は例年80日程度としている。
自然保護団体は「今は予防原則に則り、生息状況を把握するほうが先」と反発
とはいえ、絶滅を憂慮する声は強い。ネットでも、
「経営を考慮する必要あるのだろうか。まさに絶滅か存続かがかかってる種のことだけを考えるべきなのでは」
「高知県はうなぎを絶滅させる気満々だな」
と危ぶむ人が多くいる。
日本自然保護協会で保護室長を務める辻村千尋さんも、「採捕期間延長は、自然のウナギの個体数に影響しかねない」と、高知県の決定には反対だ。
「ここ30年のウナギの池入れ量を見ても、資源全体として減っていることに変わりはありません。すぐに絶滅するわけではありませんが、今は予防原則にのっとり、生息状況がどうなっているのかモニタリングするほうが先でしょう。漁をする人たちも、この先捕れなくなるよりは、一時的に我慢して控えるのが得策だと思います」
今回の高知県の決定が、他の自治体に影響することも懸念する。
「他の都道府県が追随してしまうと、資源管理もなにもない。他より短いから良いというのではなく、決めた期間を守ってほしいです」
高知県は3月20日まで漁を続けるとしている。