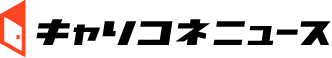発達障害かも?と思ったら「ゲーム感覚で人生の作戦を立てればいい」 ライター・姫野桂さんに聞く「生きづらい人」の生存戦略
姫野さんは、ジェンダーや貧困などの社会問題を取材する過程で、貧困者に発達障害のような特性を持つ人が多いことに気づいた。さらに発達障害の当事者に話を聞いていくうちに、「グレーゾーン」の存在を知ることになる。
「発達障害の疑いがあって病院に行ったのはいいけれど、『傾向がある』とだけ言われて診断がおりない人たちがいます。その人たちは、精神障害者手帳を取れるわけでも、障害者雇用を受けられるわけでもない。でも、仕事も人間関係も上手く行かなくてどうしたらいいんだと悩んでいる。支援の手が一番届いていない人たちだと分かってきました」
「グレーゾーン」は、定型発達・健常者(シロ)と発達障害(クロ)の間に留まっている人を指す。発達障害の特性を自覚しても診察を受けたことが無い人、一度は発達障害でないと診断されたものの、他の病院で再度診断された人なども含まれる。
姫野さんが取材した中では、発達障害当事者とグレーの人たちでは、社会生活の送り方にも違いが見られたという。一番の違いは会社での立ち位置。診断がおりている人に比べて、グレーの人は取材でも顔や氏名を出すことに抵抗がある人が多かった。職場や周囲にグレーであることを隠しているためだ。
グレーの人々の中には、努力すれば定型発達の人と変わらない状態を作れる人もいるため、さらに存在が見えにくくなっている。本書には「ある意味、障害者手帳を取得しているような発達障害当事者よりも、SOSをあげづらい」とあった。このため、支援の手を伸ばそうにも伸ばす先が分からないというジレンマも生じている。
「発達障害=すごい人」ではない「多くの当事者は社会的に困難を抱えている」
発達障害当事者やグレーの人にとって、現代は受難の時代だ。得手不得手の差が激しい当事者・グレーの人も仕事ではマルチタスクをこなす必要があり、就活ではやたらとコミュ力が求められる。
「昔は頑張れば頑張るほどリターンがありましたが、今はそうではないので、当事者は更に生きづらくなっていると思います。バブル期は、仕事ができない人には窓際族という居場所がありましたが、今はそうした人たちは最初に首を切られてしまう可能性があります」
また、発達障害が広く知られたために「発達障害=すごい人」という新たな誤解も生まれてしまった。当事者の中に、特定の分野で並外れた力がある人がいることは確かだが、姫野さんは「多くの発達障害当事者は社会的に困難を抱えているし、苦しむ人の声は埋もれている」と指摘する。
「秀でたものがあっても、気づいていなかったり育てられる環境がなかったりすると難しい。発達障害を公表しているピアニストの野田あすかさんは独自の譜面の読み方を編み出したそうですが、そういうのをサポートする人が周りにいたと思うんですよね。環境の面が大きいと思います」
「人に頼ることは格好悪くない、頼れるほうがすごい」
本の後半では、姫野さんが取材中に見聞きした、当事者やグレーの人たちの「生き抜く方法」が紹介されている。特別な能力がない当事者、グレーの人だけでなく、定型発達の人にも参考になる部分が多い。
例えば、マルチタスク対策では「パソコン画面で複数ウィンドウが開いていると混乱しやすくなるので、2つ以上開かないようにしている」、片付けられなさを克服するためには「家の物すべてに”定位置”を決める。置き場所を決めていない物は基本的に買わない」といった具合だ。気力や根性ではなく、周囲の環境や仕組みを作って困難を取り除こうとしている点が特徴だ。
姫野さんが本書で伝えたかったのは「グレーゾーンだからといってあまり思い悩む必要はない」ということだという。「ゲーム感覚で人生の作戦を立てればいいのだ」という一文にも、その思いが込められている。
「発達障害は、出来ることと出来ないことの差がある、それ以上でもそれ以下でもないと思います。困ることがあったら本で紹介したようなテクニックやツールに頼れば良いんです。人に頼るって難しいじゃないですか。特に男性はジェンダー的な背景もあります。でも、頼ることは格好悪くない、頼れるほうが実はすごいって思ってもらえたら良いなと思います」
定型でもグレーでも誰でもできないことはあるし、「できる」「できない」の程度も人によって違う。結局、それを知った上でどう活かすかが大事、と気付かされる一冊だ。