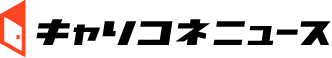生徒の成績で教員を評価、大阪市の施策は「教師の軋轢生み授業の質下げる」教育コンサルが苦言

適切な運用は守られるのでしょうか
大阪市教育委員会は2020年度から、同市や府教育委員会が実施する学力テストの成績を、小・中学校の校長の人事評価に反映させる。各学校で偏差値の向上目標を設定させ、その達成度が校長の人事評価に直接影響する形だ。目標達成や結果向上に成果が見られた学校には、特別予算を重点的に配分することも決まっている。
2月4日の『モーニングCROSS』(MX系)に出演した教育コンサルタントの中土井鉄信氏は、この施策を受け、「学校改革にインセンティブはマイナス」と苦言を呈した。このシステムだと、校長が教師を評価する際に、担当クラスのテスト結果を加味する恐れがあるためだという。
「学校は多様な子供達がいて、いろんな良い点を見て指導していく。それを、インセンティブを1つに与えたりある数値に与えたりすると、そういった部分が切り捨てられ画一化していく」
学力テストでは測れない子どもの良さが伸びなくなると危惧した。(文:石川祐介)
テストでいい点を取らせ、自分の評価を上げるための授業が蔓延しかねない
中土井氏は続けて、このシステムを導入すると、学校が子供達に良い点を取らせるためにテストの”対策”するようになると懸念する。学校教育は本来、子供が社会に順応していくための能力を育む場だが、教師を生徒のテスト結果で評価することになれば、良い点を取らせるための授業をするようになってしまうという危惧だ。
また、教師間に競争原理を持ち込むと授業レベルが下がるとも指摘する。
「重要なのは教師間の切磋琢磨なんですよ。それは協働でしか生まれない。スキルのある先生とない先生が協働で作業すれば、スキルのない先生にもスキルが出てきます。(中略)見本があって『どう取り組むのか』っていうことがない限りは、教師の授業は上がらない」
授業の質は教師間の密な連携で変わる可能性が大きいのに、この施策では教師同士の対抗心を煽るだけだと分析。その結果、授業の質が落ち、子供達の成績も悪くなる悪循環を引き起こしかねないという見方のようだ。
クラスの成績がふるわない教師が、好成績のクラスを、「あいつは良いクラスを持ったな」とやっかむことも考えられる。教師にとって子供の価値が、テストの成績だけになってしまうと警鐘を鳴らしていた。
「学力を上げるための教師ではない。子供を社会構成メンバーにするために、今目の前にある課題に子供達が真剣に取り組める力を与えることが教育。その結果テストの点数が取れるようになる。点数を取るために何かをするんじゃない。発想が間違っている」
子供が学びやすい環境を整備すれば、テストの成績も自ずと上がっていく。中土井氏は、大阪市の施策は見直すべきという主張を一貫して変えなかった。