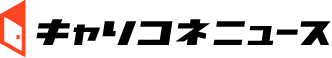ニッポンの漁業を盛り上げる驚異の「鮮度保持技術」 解凍した4年前のタコが吸い付く
シンガポールの街角で日本食について聞くと、「スシが好き」と答える人が多い。しかし日本食レストランでは、チリやノルウェー産のサーモンが一番人気。お客も「日本のスシはサーモンが一番ね」と話すという。
つまり日本の漁業は、世界の日本食ブームの恩恵を受けることができていないのだ。2015年4月13日放送の「未来世紀ジパング」(テレビ東京)は、この状況を打破して新鮮な「日本の魚」を世界に発信するため、開発された新技術を伝えた。
「命は消えても、細胞は生きている」
千葉県流山市にあるアビーは、魚を獲った時の鮮度を保ちながら冷凍する技術を持っている。冷凍庫で冷やした4年前のタコを解凍したところ、吸盤に触った指が吸いついてくるほどの鮮度を保っていた。
3か月前のものなら更に新鮮で、指に吸いついた吸盤でタコの足が持ちあがる。アビーの大和田哲男社長は、「生命体としては死んでいるのですが、細胞は生きていることが分かります」と説明した。
秘密は「CAS(キャス)付き冷凍庫」という、凍らせるだけではなく磁力や光・音など8つの力を加える特殊な冷凍方法だという。この技術を視察に訪れたニュージーランドのピザ会社やイタリアの小麦会社の人たちは、一様に驚いていた。
解凍した1年前の岩ガキを試食して、「素晴らしい。完璧」「フレッシュ!」と感嘆。にぎり寿司や具入りの鍋など、料理ができあがった状態で冷凍し、そのまま保存できるようにもなっている。
福岡・小倉では、魚を生の状態で輸送する「ナノ水」という技術を丸福水産が開発し、愛媛や長崎の魚をカナダへ出荷していた。氷水に10分魚をつけ、体内にナノレベルの小さな泡で窒素を送り込むことで鮮度を保つ。カナダの仲卸会社からはLINEで発注が来ていた。
岐阜の富士商工は、魚が生きている状態を長く保つ技術を開発。装置に入れて50分間加圧することで魚を仮眠状態にし、水なしで冷蔵しても生きている。まだ研究段階だが、開発者の永井さんは「この装置を使って海外に販路を広げてもらい、水産業界を維持してほしい」と語る。
東南アジアへの物流体制も確立中
日本経済新聞社・編集委員の後藤康浩氏は、こう解説した。
「日本のように魚を生で食べる習慣の国は世界にあまりないので、日本は魚を生かす技術、新鮮なまま輸送・保存する技術は世界トップと言っていい」
日本から東南アジアへの物流体制も確立した。青森特産のヒラメが朝出発し、翌日の昼には生きたまま香港へ届く。沖縄の那覇空港をハブとして、東南アジアの主要都市までは4時間以内に届くという。
魚は、先進国ではヘルシー志向、途上国では肉よりも安いタンパク源として、世界的には消費量が増加傾向。ただし売っただけでは駄目で、「保存管理や調理も日本式にこだわらないと、かえって日本の魚の名声が落ちてしまう」と後藤氏は釘を刺した。
番組では、15年前には魚の消費量は日本が世界1位だったが、最新の調査では3位になったと伝えた。今後、日本では減少傾向にある漁業が、他の国へ輸出することで盛り上がっていくことを期待したい。(ライター:okei)
あわせて読みたい:取締役が全員アルバイト出身の居酒屋チェーン「鳥貴族」