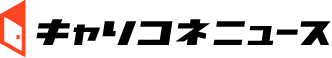バブル世代の就活では、履歴書を出すだけで内定がもらえた、というのはよく聞く話だ。一部の企業では、他社に内定者を取られないために、3S(ステーキ・しゃぶしゃぶ、寿司)で接待したり、内定者をリゾート地のホテルで”研修”したりするところまであったという。
売り手市場だった当時の新卒採用を描いた映画『就職戦線異常なし』(1991年)では、織田裕二さん演じる主人公たちが高級ディスコのVIPルームで接待を受ける場面がある。その後、主人公はマスコミの最終面接まで進むが、結局は食品会社に入社。「本当の就職とは何なのか」と自問自答するストーリーだ。
就職氷河期世代の筆者が経験した2000~01年の就活といえば、エントリーシートや履歴書の段階で何十社も弾かれた。ようやく面接にたどり着いたかと思えば、十分な自己アピールもさせてもらえず、面接はすぐに終了。数日間経ってから「お祈りメール」が送られてくるのはまだマシな方で、何のアクションもないまま連絡を切る会社すらあった。
結局100社以上にエントリーした後に、どの企業からも内定をもらえず、大学在籍中に働いていた飲食チェーンのアルバイトを続けざるをえなかった。そういう経験者からすれば、バブル世代があっさりと内定がもらえて接待まで受けるというのは、にわかには信じられない。
同世代の中には「生まれた時代が違った」というだけでは、到底納得できない人も多いのではないだろうか。筆者もまた、その一人だ。
就職氷河期世代の就活、誰も頼れず「自己責任」に
特にバブル、就職氷河期の両世代を隔てているのは、それまではあった卒業生同士の繋がりが切れているケースが多いことだろう。バブル世代まではOB・OGを訪問することが内定獲得の近道だった。
だが、就職氷河期世代の場合はそもそもの採用枠が狭すぎていて、OB・OGを訪問する意味が薄れていた。だから、先輩から人生の転機となる口利きをしてもらったり、社会人としてのノウハウを学んだりする機会は圧倒的に少なかったように思う。
つまり、新卒採用に失敗した就職氷河期世代は「自己責任」のもと、先輩から手を差し伸べられることもなく、自力ではい上がる以外に道はなかった。
両世代の差は、年収を見ても明らかだ。厚労省の賃金構造基本統計によると、大卒で同じ企業に就業している場合、1967年生まれが40歳時の年収は787万円に対して、筆者が生まれた76年生まれの40歳時の場合は709万円と、78万円の差がある。当然ながら、多くの就職氷河期世代のように何度も転職を繰り返している場合は、年収格差がさらに広がる。
このような差は、バブル崩壊による景気後退が生んだもので、バブル世代の当事者たちに罪はない。
だが、十分にキャリアアップの機会が与えられて、生涯年収に差がつくことも確定している中、会社内のイスに座っているだけで給料がもらえる身分でいるように、どうしてもバブル世代のことを見てしまう。
バブル世代もまた、そういった視線に居心地の悪い思いをしているのではないだろうか。それこそが両世代をさらに隔てる「壁」になっているように感じられるのだ。