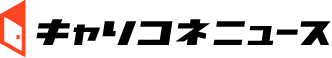そこにあるのは「伝えたい」という想い。報道の第一線を走り続ける使命

▲「シリーズ老障介護」2020年度ギャラクシー賞受賞
報道局ニュース情報センターで、報道特集の制作を行う西村 美智子。じっくり時間をかけて取材先と向き合い、数々の問いを世の中に投げかけてきました。「伝えたい」という使命感で、報道の最前線を走り続ける彼女。その原動力は、どこにあるのでしょうか。【talentbookで読む】
事実を取材し、社会に問いかける。報道という仕事の意義と使命
朝日放送テレビ(以下、ABC)の報道局ニュース情報センターに所属し、日々ニュースを追い続けている西村 美智子。事件・事故、災害、医療福祉、そして健康。人々の生活に関わるさまざまな分野にアンテナを張り巡らせ、番組を通して情報を伝えています。
西村 「取材をするのはもちろん、どんな表現で視聴者に伝えるのかまで考えるのが、テレビ局の報道記者の仕事です。中継で伝えるのか、スタジオに出て解説するのか、VTRで表現するのか。番組に落とし込むところまですべてに責任を持ちます。
現在は、日々のニュース取材と同時に、夕方の報道番組『newsおかえり』の特集コーナーを担当しています。10~15分のほどのVTRを流すために、企画立案から取材、台本づくり、編集・校正までやっています」
西村が担う「報道番組」は、新聞や雑誌などから得た情報を提供する形ではなく、ゼロから取材した出来事を伝えることを目的としています。
西村 「取り上げる情報はすべて1次情報。他のメディアがまだキャッチしていないニュースを取り上げることもあります。独自の視点、独自の感性で『このことは知っておいたほうがいい』というテーマを探して、お伝えする。その独自性にこそ、報道の意義があると感じています。
そのため、この仕事には感受性や知見が欠かせないと感じています。社会にとって、視聴者のみなさんの暮らしにとって、何が大切なのかを客観的に見つける力が必要なんです」
西村の現在の役職は、管理職を指す「プロフェッショナル」。1人の記者として現場で活躍しつつも、能力や経験を次の世代を担うメンバーへ伝えています。
西村 「見落とされている大事なことや、これから問題になりそうなことを見つけるという、重要な使命が私たちにはあります。取材し、番組というかたちにしてお届けし、社会に向けて『どう思いますか』と問いかける。そうした意義のある取材の姿勢を伝えるようにしています」
事件・事故を目の当たりにする日々。報道記者としての使命に気づく

西村が入社したのは、1997年のこと。当時は就職氷河期でした。
西村 「ちょうど世の中が180°変わり、厳しい就職活動になったタイミングでした。人間の価値って、時代によってこんなに左右されてしまうんだと衝撃でしたね。就活中は、自分にはどんな価値があるだろうかと悩んだのを覚えています。
一体何を生きがいにしたらいいんだろう。そう考えたとき、どんなに些細なものでもいいから、モノを生み出したいと思ったんです。自分で何かを作れば、たとえ小さなことでも生きがいを感じられるんじゃないかって。そこで興味を持ったのが、テレビドラマやバラエティ番組を作る仕事でした」
テレビ局に入って、視聴者のみなさんに人間ドラマや笑いを届けたい。そんな憧れでABCに入社。しかし、希望通りの配属とはいきませんでした。まずは宣伝部とラジオ制作部で勤務、入社8年目となる2004年に、報道記者としての内示が出ます。
西村 「報道局に配属されることを知ったときは、ドラマやバラエティへの道はもう絶たれたなと感じました。でも年齢的にも30歳になっていたし、受け止めて報道記者としてやっていこうと決意しました。
実際にやってみて感じたのは、ノンフィクションの現場も、非常にクリエイティブな世界だということ。自分の足で歩いて見つけた世界に、自分で取材交渉して、話を聞いて、原稿を書いて、VTRにまとめる。そのやりがいに徐々に気づいていき、いつの間にか報道の世界でずっとやっていきたいと思うようになっていました」
西村が報道記者になって約1年が経った、2005年。兵庫県尼崎市で、JR福知山線の脱線事故が発生し、100名以上の方が亡くなりました。西村は、この事故を取材しています。
西村 「亡くなった方、突然遺族になった方、そして負傷した方を取材しました。たまたまその電車に乗っていたことで被害に遭った方がいる一方で、たまたまその次の電車に乗って被害を逃れた方もいる。そんな不条理な状況と向き合いました」
当時の西村は、警察担当記者として殺人事件の取材も経験していました。事件・事故への取材を通して感じたのは「世の中には、伝えなくてはならないことがこんなにあるのか」という驚きでした。
西村 「なんの落ち度もない方が突然亡くなるという事件・事故を目の当たりにし、自分と、被害者の方との違いはなんだろうと考えました。自分だって、いつ被害者になってもおかしくない。そう考えたとき、世の中には、被害者を支える制度が足りているのか、温かい眼差しはあるのかと、疑問に思うようになります。
世の中には足りないものがたくさんある。その不足を世に訴えるのは、被害者の仕事ではなく、報道機関の仕事なんだ。そう気づき、報道記者の使命に目覚めていきました」
世の中という大きな輪の中で、報道の仕事は、ひとつの社会的な役割を担っています。その事実が、西村の原動力のひとつになりました。
震災復興をテーマにドキュメンタリーを制作。「取材にゴールはない」

その後、報道番組の制作に関わるようになり、ご遺族や高齢者、障がい者など「社会的弱者」と呼ばれる方々と向き合うことになった西村。心を開いていただくことの難しさに直面します。
西村 「テレビなので、お話を聞くだけでなくカメラを向けます。食事シーンなどのプライベートも撮影します。どうやったら相手に心を開いてもらえるのか、心を開いてもらえるに足る人間になるにはどうしたらいいのか、難しさに愕然としました。目の前の方に誠実に向き合うためには、自分が人として変わらないといけないと。大変難しい仕事だと思いましたし、今もその難しさを感じながら続けています」
模索しながらも真摯な想いで取材を続け、西村はこれまでに15本以上のドキュメンタリー番組を制作しました。中でも印象深いのは、2012年に放送した、震災復興のドキュメンタリーです。
西村 「東日本大震災が起き、ABCとして復興にどう寄与できるかを考えたんです。そこで、阪神淡路大震災での教訓を発信することにしました。阪神淡路大震災では、被災した大都市を立て直すために多額の費用をかけ、再開発が行われました。
しかし、再開発に巻き込まれることで、街に暮らしている方がより不幸になってしまったという事例があって。私はそこに着目し、『この復興は正しいのか』と疑問を投げかけるドキュメンタリーを作ろうと決意します。
復興をある意味で否定する、挑戦的な切り口です。でも、復興事業が正しく行われたのか、税金の使い方は正しかったのかを検証することは、地震大国である日本にとって重要なこと。東日本大震災の教訓にするためにも、世に問いかけるべきだと判断しました」
大きなテーマを背負い、1年間取材を続けます。世の中に事実を報道することの重さ、意義、怖さが詰まった1年でした。
西村 「おかげさまで、完成したドキュメンタリー番組は、さまざまな賞をいただきました。賞を獲ったことで、取材させていただいた方々の声が正しかったことを認めてもらえたようで、ホッとしましたね。あの賞は、取材を受けてくれた方々の勇気に対する称賛だと思っています。
このときに審査員の方から言われたことが、とても印象的でした。それは、『賞を与えたのは、これからも続けてほしいからだよ』という言葉。途中で逃げるのは失礼だし、取材を続けることで恩返しができるんだと気づかされました。番組には放送日というゴールがあります。でも、取材にはゴールはないんです。受賞の達成感と同時に、新しい宿題をもらったような気分でした」
人生を通してやって良かったと思える仕事。この想いを、後輩に託したい

人々に寄り添い、報道という仕事に向き合い続ける西村。そうした中で、幾度となく苦しい想いも経験しています。
西村 「人々が抱えるつらさを報道する仕事です。世の中にこういう制度が足りない、行政が目を向けてくれない、障害があってつらい、苦しい、困っている……。そういう声を取材して放送まで持っていくというのは、正直つらいし、しんどいです。でも、『西村さんだから取材を受ける』『ありのまま喋るし、ひどい部分も撮っていいよ』と言ってくれる方々がいるんです。
事実をありのまま世の中に出すので、取材を受けてくださった方にとっては、自分のつらい部分を映像であらためて見ることになりますし、しかも世の中から見られることになる。放送後に、取材を受けてくださった方がどう思うのか、いつも緊張しています。
でも、不思議なことに、みなさん『ありがとう』って言ってくださるんですよ。そして『また取材して』と。むしろ1回のVTRじゃ世の中は変わらないから、終わらせないでほしいと思っている。だからその声が原動力になって、続けているんです。私が根っからの報道マンだから……。みたいなことでは全然ないんですよ。求められて、取材する。その連続で今があるんです」
そんな西村は、今後どのような道を歩んでいこうとしているのでしょうか。
西村 「何年も関わってきた方々が、私を信頼してくれているので、ここでやめることはありません。築いてきた関係性を大切にしながら、今後も取材を、報道という仕事を、深めていきたいです」
ここ数年、西村のもとには「報道の仕事に挑戦したい」という若い社員からの声が集まるようになりました。
西村 「こういうしんどい仕事をやりたい後輩がいるなんて、すごく不思議ですけれどね。プライベートのオンオフの切り替えは難しいし、取材先のスケジュールに合わせて休みの日も動きます。節度ある姿勢で取材に臨めるように、プライベートもある程度制限されます。
それでも話を聞きたい、自分もやってみたいという声があるなら、大きく門戸を開いていきたいと私は思います。若い社員と2人で会話する機会を作って、人生設計ややりたい仕事をじっくり聞くようにしています」
「後輩へ伝えていくことも、自分の使命になっていくだろう」と語る西村。
西村 「というのも最近、取材先の方々から『西村さんがやめたら、この取材はどうなるんですか』と聞かれるようになっています。今後のためにも、後輩を育てて、想いを引き継いでいきたいです。
今はネットメディアなどの新しい媒体が報道の世界に参入していますが、プロの目線でフィルターをかけて、凝縮した情報をお届けするというのは、大きいメディアにしかできない使命です。
充実感もしんどさもありますが、人生を通してやっていけて良かったと思えるような仕事なのは、間違いありません。だから、興味を持ってくれる方にはぜひ参入してもらえればと思っています」
記者として第一線を走りつつ、後輩に想いを託す西村。ひたむきな背中を見せつつ、ときには手を引き、報道局を頼もしく導いています。