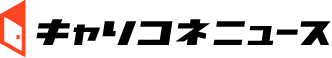家庭の経済状況による子どもの学力差は8歳以降に拡大 「逆転は学年が上がるほど困難になる」
貧しい家庭の子どもとそれ以外の家庭の子どもでは、幼少期に能力差がついてしまうようだ。日本財団は11月20日、「家庭の経済格差と子どもの認知・非認知能力格差の関係分析」を発表した。

生活保護世帯の子どもとそれ以外の子どもの偏差値の推移
生活保護世帯の子どもの国語の平均偏差値は、8歳で49.6まで上昇した後、10歳で45.1まで低下し、以降40%台で推移することが明らかになった。一方、困窮していない世帯の子どもの平均偏差値は8歳の50.1から上昇を続け、14歳では53.1になる。両者の学力差は8歳以降、拡大してしまうのだ。
偏差値45以下の子どもが翌年45以上になる割合は10歳以降、20~30%しかない
同財団は、大阪府箕面市の「子ども成長見守りシステム」によって収集された、同市の全ての子ども(0~18歳)約2.5万人のデータを分析した。

低学力は固定化する傾向に
偏差値45以下の子どもが翌年に偏差値45以上になる割合は、8歳では42.2%だが、9歳では37.1%、10歳では27.5%にまで低下する。11~13歳にかけては上昇するが、14歳では23.9%まで低下している。低学力の子どもが偏差値45を超える可能性は、10歳以降、20~30%程度しかないのだ。
差が見られるのは、学力テストで測定できる「認知能力」だけではない。自制心や勤勉性などを表す「非認知能力」についても差が見られた。
生活保護受給世帯で「勉強、スポーツ、習い事、趣味などで頑張っていることがある」と回答した子どもの割合は小学校から中学校にかけて7~8割で推移している一方、それ以外の世帯ではいずれの学年でも9割以上に上っている。
「朝ご飯を毎日食べている」と答えた子どもの割合にも同じような傾向が見られた。生活保護世帯では60~70%台で推移している一方、それ以外の世帯では9割以上をキープしている。
「格差が拡大する前に、早期に支援が行うことが必要」
また、「辛いことや困ったことを学校の先生に相談できる」と回答した貧困世帯の子どもの割合は、小学校1・2年の83%から中学校の34%まで低下。同回答に関しては、それ以外の世帯でも83%(小学校1・2年)から52%(中学校)まで減少しているものの、学年が上がるにつれて両者の差が拡大していることがわかった。
これらの「非認知能力」は「認知能力」の発達を促し、将来の所得にも大きな影響を与えることがわかっている。8~9歳で最も家庭環境の影響を受けやすく、この時期に恵まれない環境で育った子どもは、その後の学業成績や所得でも不利益を被る可能性が高い。
しかし残念ながら、学童保育はこうした能力差の解消に効果を発揮できていないという。学童を利用した子どもと利用していない子どもの能力を比べても、有意な差がなかったのだ。
同財団では、「低学力の子どもが、低学力層から脱出できる可能性は学年とともに低下し、逆転が困難になる」ことから、「格差が拡大する前に、早期に支援が行うことが必要」と訴えていた。
※ウェブ媒体やテレビ番組等で記事を引用する際は恐れ入りますが「キャリコネニュース」と出典の明記をお願いします。