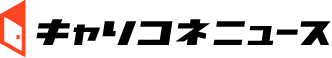仕事第一!でもがんばり過ぎ?――社畜女子が、父の迷惑な行動に呆れながらも自分を取り戻す映画『ありがとう、トニ・エルドマン』

(C)Komplizen Film
「お父さん、なんでこんなことするの!?」――そう叫びたくなるような無神経な行動、くだらない嘘……当時はよく分からなくても、後々それが父親なりのコミュニケーションだったと気付いた、という人もいるだろう。
映画『ありがとう、トニ・エルドマン』(独 監督:マーレン・アデ)は悪ふざけが大好きな父親・ヴィンフリート(演:ペーター・ジモニシェック)と、外国のコンサルティング会社で”バリキャリ女子”として働く娘・イネス(演:ザンドラ・ヒュラー)の物語だ。
……と書くと「ユーモアのある父親が、仕事熱心過ぎる娘の心を楽にしていくコメディ調な感動映画かな?」と思ってしまう。たしかにその一面もあるが、娘を心配するヴィンフリートの愛情表現が不器用すぎて迷惑行為にしか思えない。
それでも衝突を繰り返しながら二人の仲が縮まっていく。そんな二人の関係を温かさと冷静な視線をあわせ持った絶妙な温度感で描いたのがこの作品だ。
ムカついてもイラついても、親子ってこういうこと

(C)Komplizen Film
久々の家族団らんの場でも電話片手に対応に追われているイネス。そんな娘を心配したヴィンフリートは、突然ドイツからルーマニア・ブカレストにあるイネスの職場を訪れる。しかし大きな仕事を前に、中々父親には構っていられない。
やっと父親が帰った、と安堵するのも束の間。ヴィンフリートは長髪のカツラを被り出っ歯の入歯を入れ、別人”トニ・エルドマン”としてイネスの元に現れる。職場、レストラン、パーティー会場……神出鬼没の”トニ・エルドマン”の行動に、イネスのイライラが淡々と描かれている。
すべて娘を思うが故の行動だが、ヴィンフリート自身が楽しんでいるフシもある。一方でイネスは仕事が第一。オフも自ら顧客の妻の買い物に付き合い、異性にもパーティーにも心がときめかない。しかしさすがこの父親あっての娘。父と過ごした時間から、イネスの中で何かが変わっていく。
実はこの映画、『ムーンライト』や『ラ・ラ・ランド』を抑え、各国の有力誌から2016年の映画ベスト1に選ばれている。カンヌで大きな話題になるとアカデミー賞ノミネートをはじめ、各国で40を受賞し、すでに公開されているドイツ・フランスでは大ヒットを記録している話題作なのだ。
アデ監督「自分の身をまっさらにすることへの賛歌」

(C)Komplizen Film
まず念頭に置きたいのが、イネスは微塵も「仕事がイヤ」と思っていないという点だ。男社会の中でも上昇志向が強く、常に張り詰めた表情でバリバリ働く企業戦士。戦闘服のようにスーツを着て仕事に打ち込む姿は、日本の働く女子と同じだ。
そんなワーカホリックからすれば、パーティーやセックスなどですら「仕事の妨げ」としか思えなくなってしまっていることもあるだろう。
父親は、仕事に追われる娘を見て「本来のイネスと遠ざかっているのではないか」と心配している。だから「ここにいて幸せか?」と問いかけるし、もっと他に楽しいことをしてほしいと願っている。父親の愛情はほぼ迷惑行為の連続ではあるが、その愚直な思いがイネスに”好きで仕事をやっていたはずが、本当はいろんなものにがんじがらめにされていた自分”を気付かせる。
アデ監督はこの映画について「解放への賛歌というより、自分の身をまっさらにすることへの賛歌なのです」と話している。
「イネスが最後にすることはかなりラジカルで大変な勇気を必要とします。でもそれは新しい始まりなのです(略)。彼女は何も解放していない、ただ手綱を自分の手に取り戻したのです」
ただこれは父親と、大人になった娘の普遍的な物語でもある。すべて父親が娘の問題を解決するわけではない。自分の未来は自分で切り開いていかなければならない。それでも「父と娘」であることに救われることもある。アデ監督はこう語る。
「(毛むくじゃらで大きな)クケリの衣装がヴィンフリートを変えた。それでほんの一瞬、イネスにとって彼は子どもの頃知っていた、大きくてよたよた歩く、心温かい父親に見え、彼女はかつでそうだった”少女”になれるのです」
労働先進国のドイツから生まれた『ありがとう、トニ・エルドマン』は父と娘の関係性を通して、”働き方”を考える上で大きなヒントをくれる。終盤、イネスのある選択は「働きながら幸せになるには」という観客への問いかけとも取れるだろう。
映画『ありがとう、トニ・エルドマン』は6月24日(土)シネスイッチ銀座、新宿武蔵野館ほか公開。