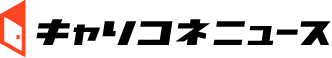女性は教員になる前に、新卒で入社した一般企業に3年ほど勤めた経験がある。「歴史の教師になりたい」という思いから退職し、大学院に入り直した。その後、教員採用試験に合格、20代後半から高校教師としての人生を歩み始めた。ところが、滑り出しは順風満帆とは言い難いものだった。
「初任校、つまり最初に赴任した学校はいわゆる教育困難校でした。生徒に厳しい指導をすることが求められたのですが、それがなかなかできず『生徒の素行が悪いのはお前がちゃんとしないからだ』と職員室で先輩教員からずいぶん責められるなど、今から思えばパワハラもありました」
その初任校では超過勤務や休日出勤にも悩まされた。こうした労働環境の理不尽さに対し、「それはおかしい」と主張し続けると、次第に孤立していった。仕事も人間関係もうまくいかなくなり、職員室では同僚とも口をきかず、「能面のような顔」で約2年を過ごした。
任期満了で2校目に赴任するも、配属先は「図書課」だった。授業以外の時間はひたすら図書周りの仕事をする課だ。女性は30代だった当時の心境をこう語った。
「えっ…なにそれ…という感じでした。普通、図書担当だけで一つ課ができるということはないので、どんな仕事をするのかもよく分かりませんでした。職員室に席がないのも、ああ、戦力外なんだなあ…と思いました。これは想像ですが、前の学校の校長から、転勤先の校長に、『こいつは使い物にならない』と申し送りがあったと思います」
周囲とのコミュニケーションに難がある人が行く課だった
校舎内に設置された図書室とは違い、この学校の場合、校舎とは別の独立した建物でいわゆる図書館だった。図書課は図書館内にあった。一体どのようなものだったのだろうか。すると女性は、
「正直謎です。図書課が学校運営の中で何か意味ある役割を持っていたとは思えないです。あとから理解したのですが、図書課というのは、担任や生徒指導など授業以外の仕事を上手くこなせない人、周囲とのコミュニケーションに難がある人が行く課でした」
と明かした。図書課には女性の他に2人の教員が配属されていた。まず、課長はベテランの男性教諭で、病気のため長いこと図書課に勤務していた。「いいかい、職員会議はね、1年目は発言するもんじゃない。にこにこ笑って座ってなさい」と、お茶をすすりながら教師としての処世術を教えてくれた。
もう1人は、当時40代後半の男性教員だった。
「めちゃくちゃ頭が切れるけど、周囲と合わせることを全くしないので、担任を下ろされて図書課配属になってました。これはたぶん左遷の範疇ですね」
図書課で過ごした1年間を女性はこう振り返った。
「私の机はカビ臭い司書室にありました。そこで、ほぼ日がな一日、新しく来た本にカバーをかける仕事をしていました。本の入荷などの業務はベテラン事務員さんがやっていたし、本棚の整備やちょっとした貸し出し業務はしましたが、私はただひたすらカバーをかけていました。そもそも私は司書教諭の免許を持っていませんから……」
図書館は人づき合いの苦手な生徒が隠れにくるくらいで、いつも閑古鳥が鳴いていた。誰かの悪口を言いたい教員が、職員室と交流のない女性に、たまに「王様の耳はロバの耳」をやりにくることはあったが、それ以外で教員が来ることはほとんどなかった。
そうした日々のなかで女性はカビにやられたのか、気管支の病気になってしまう。2週間ほどで復帰できたものの、辞めたくならなかったのだろうか。
「辞めようとは思わなかったですね。仕事干されたなあ…とは思いましたが、前の学校を出られた解放感の方が遥かに大きかったです。時間も山ほどありました。面白い歴史の授業をしたいというのが私の教師としての目標だったので、ほぼ仕事がない時間を教材研究に振り向けました」
話を聞いてくれた課長の存在も大きかった。「ふうん、そうなのね」と相槌を打つ程度だったが、それが女性には心地よかったのだろう。また、課長も歴史の先生で、歴史研究や歴史教育についてよく語り合った。
「変な話ですが、左遷された場所で初めて、『こういうことがしたくて教師になったんだよな』と思いました」
図書課で“リハビリ”「削られ続けていた自己肯定感がゆっくり回復した」
初任校は教育困難校、そのうえ先輩教員からパワハラを受けていた女性にとって、司書課で穏やかな日々を過ごしたことは心の回復につながった。
「当時はあまり自覚がありませんでしたが、おそらく、削られ続けていた自己肯定感がゆっくり回復したんだと思います。職場の人間関係はほぼできませんでしたし、何のスキルも身につきませんでしたが、『お前は仕事ができない』と非難されることに疲れ切っていたし、怯えていたので、仕事も人間関係もシンプルにしてカームダウンすることはできました」
こうして図書課での“リハビリ”を経て、クラス担任に復帰した。初任校での反省から「とにかく生徒のほうを見て、生徒のことを第一に考えよう」という女性を同僚は温かく見守ってくれた。生徒には「来年も先生のクラスがいいな」と言われ、嬉しかったそう。さらに、
「管理職からも『よく働くわねえ』と評価してもらえるようになり、歴史教育のカリキュラム開発がしたいという私の希望も好意的に受け取られました。数年後に、カリキュラム開発を専門的に行う国立の研究開発校への転職が決まりました」
と夢を叶えた女性。左遷から数年ほどでの出世は一般企業では珍しい光景ではないだろうか。
「教員の世界では出世の概念があまりないため、そもそも左遷とはどんな状態か判断するのは難しいところです。ただ、クラス担任は最フロント業務で、学校の花形でもあります。私がいた図書課がその対極に位置していたのは間違いないでしょう。それでもあの1年は今思えば必要な1年でした。誰からも期待も認知もされませんでしたが、課長はそんな私を心配するでも、放置するでもなく、穏やかに眺めてくれていました。課長とカビ臭い小さな部屋で過ごした『左遷』の1年に、感謝したいと思います」
左遷を必要な経験だったと捉えている女性。課長との出会いが大きいだろうが、現在も勤務している国立の研究開発校で充実した日々を送っているからこそ言えることだろう。
超安定企業で32歳のときに“左遷用職場”に飛ばされた男性 「今日もやることなし。業務終了」なのに平均以上の高収入だった