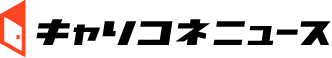「全てを自分たちの手で」ファンケルが基幹システムの完全刷新「FITプロジェクト」で2025年の崖を乗り越えた裏側
――植松さんの視点から御社がどのようなDXの軌跡を辿ってこられたのか、ぜひ教えてください。
私が入社したのは1993年、ファンケルがまだまだ小さな会社だった頃です。新卒入社で当時プログラマーとしてIT部門に配属されました。ファンケルはその当時から基幹システムを内製化していたんですね。まず通信販売の仕組みを、ベンダーの力を借りながら自分たちで作るというところから始まりました。
当時はとてもベンチャーな企業でしたので、創業者の池森がアイデアベースに色々なことを始めるんです。その都度、仕組みやシステムを作っていく、「新しい事業=システムを作る」という、ものづくりが我々IT部門の仕事の中心でした。
大きな変革点となったのは2000年です。
当時、どこの大きな企業もIT部門は専門的な大手企業にアウトソーシングするという流れが起き始めたんですね。当社もその流れに乗ってIT部門を解体し、大手ベンダーにアウトソーシングする方向に切り替わりました。それまで行っていた内製化をやめてアウトソーシングを管理する情報システム部を残すのみになり、人員も他部署の兼任部長と私のみ。「アウトソーサーと管理者」という道に進んでいきました。
「全てを自分たちの手で作り上げる」DNAを呼び起こす基幹システムの刷新「FITプロジェクト」が始動
その頃から会社はどんどん急成長していきました。化粧品と健康食品の事業が育っていき、通信販売だけではなく店舗販売、それから流通販売と呼ばれるドラッグストアやコンビニ店頭への展開、この3つの販売チャネルを持つようになります。
事業が拡大していく一方で、IT部門についてはアウトソーシングをどんどん進めるのですが、やはり課題が生まれてきます。システムの老朽化です。
2000年に作った基幹システムの仕組みは変えられることなく、どんどん古くなっていました。事業が増える中でシステムだけが肥大化していくのです。
当然、このままでは大変なことになると、2005年と2010年に2度再構築プロジェクトを立ち上げるんですが、2回とも失敗してしまいます。
――失敗の理由はどんなところにあったのでしょうか。
2つあります。一つは費用が高額すぎること、そしてもう一つは目的意識でした。
システムを新しいものに作り直すとはいえ、ほぼほぼ機能が同じものを作り直すのに20億や30億なんて金額がかかる、それは企業として到底許されないという状況がありました。
これは多分、昨今多くの企業がぶつかる壁であって、まさに「2025年の崖」の背景そのものです。我々もその壁にぶつかり、肥大化していくシステムに危機感を持ちながらも使い続けていました。
――まさに多くの企業が直面している課題だと思います。そのような状況で2014年にシステムを刷新する「FITプロジェクト」が立ち上がるわけですが、どんな背景があったのでしょうか。
腹を決めてシステムを作り直すきっかけになったのは、創業者の池森の経営復帰でした。当時池森は引退という形で一線を退き、外からファンケルを見守っていたのですが、ファンケルが衰退していくのを見兼ねて経営に復帰します。
当時のファンケルの内情は「安心・安全」の呪いにかけられて全ての仕事がものすごく過度になっていたんです。世の中にある基準を上回る「ファンケル基準」を設けて安心安全を徹底しているのですが、それゆえに何もできなくなる、しがらみとなっている。
また、IT部門に限らず外部依存をしていました。自分たちでは何もやらず、外からコンサルを連れてきて全てそこに任せて「できました」「やりました」と言っている状況があった。自分たちの手で作り上げることが文化でありDNAであるファンケルが、自らの手を動かしていないのです。
ファンケルはいつからそんな大企業になったんだ、「外部依存をやめてしまえ」という言葉を池森が放ったんです。
この、池森の復帰のタイミングと方向性がIT部門の抱える問題にうまく刺さり、池森が完全にバックアップに回ってくれました。これが「FITプロジェクト」の入口ですね。
5,000本ものプログラムを解析し圧縮。全プログラムの作り直しを1年で完遂

――基幹システムの総入れ替えとなる「FITプロジェクト」、具体的にはどのような内容だったのでしょうか。
当時基幹システムと呼ばれる仕組みは5,000本のプログラムからなっていました。しかもそのプログラムはベンダーの専門用語(RPG)で組まれていて、それに対応できる技術者も多くありません。
それでも、数名の読める人間と読めない人間と、私も含めて5,000本のプログラムを全て解析しました。プログラムを2,000本まで圧縮して基幹部分を作り上げ、基盤部分の周りにはシステムと会話できるようなAPIをたくさん作りつけるわけです。
また、ベンダー専門用語で組まれたデータベースのデータの移行も同時に実行していきました。そうして新たな基盤を作る構想を同時に練りながら実現していき、2016年までのおよそ1年間で基盤部分の構築が完了しました。
――たった1年という期間で、基盤部分の構築を完遂されたとは素晴らしいですね。
2016年のリリース以降、半年ほどはトラブル続きで地獄を味わいました。しかしそれを乗り越えた後は、何かを直そうとしたら今までのコストの半分以下で、期間も三分の一でできるようになったんですね。
また、基盤が出来上がったことでずっと念願だった他システムとの完全連携にも着手できるようになりました。こちらも2017年から企画し、1年をかけてECと店舗システムを同時に全刷新しました。
2018年には完全連携し、お客様情報は完全に一致します。今回のコロナ禍のような事態が起きた場合でも、普段店舗で購入されているお客様をスムーズに通販へ誘導できました。減少した店舗売上を通販で回収できたというのも、コロナ対応の面で評価していただけたところです。
システムユーザーにとっても、それまで何かを依頼しても見積もりだけで1ヶ月くらい取られてしまったことが、基幹システムを刷新したことで見積もりなんて半日で「すぐやっちゃいましょう」という感じに前進するようになりました。
そうすると、人はどんどん変わるんです。あれほどまでに硬直化していて何をするにも安心安全、お客様に怒られてしまわないか、何か問題があったら大変だ、と言っていたシステムユーザーは、このFITプロジェクトによって「変わることへの躊躇」がなくなったんですね。変化を恐れなくなったことは、一番の効果と言ってもいいかもしれません。
ファンケルの価値を見える化する「新お客様DB」の構築へ
――FITプロジェクトはただ「2025年の崖」を乗り越えるだけでなく、多くの利益をもたらす非常に重要なプロジェクトであることがよくわかりました。今後さらなる展望はお考えでしょうか。
2022年春を目指し構築を進めているのは、お客様の購買に至るまでの行動情報など、「お客様を理解するためのデータ」を収集して分析する「新お客様DB」の構築です。
こうしたデータ利活用の構想は、私がIT部門にいるときからずっとやりたいと思い描いていたことであり、基盤システムを完全刷新しなければ実現できないことでした。
ファンケルとお客様ってすごく濃い関係なんです。初期のファンケルで化粧品を買っていた方が御結婚されてお子さんができて、そのお子さんに最初に勧める化粧品がファンケルの製品だったり、化粧品のユーザー様が両親の健康を思って健康食品をおすすめしていただいたり。企業に対する信頼が「大切な人」に対しても広がっていく、こういうことを普通に行われるお客様がたくさんいらっしゃるんですね。
そうした、ファンケルを好きになってくれるお客様に「なぜ好きになってもらえたのか」。それはいわば「ファンケルの価値」とも言えるでしょう。それを見える化していけば、ファンケルという会社がもっと変われるし、もっと新しいことができると考えています。
その昔、私がファンケルの創業者の池森に惹かれて入社した当時、池森はアイデアベースでいろんなことをやってきました。振り回される人のことなんて関係なくいろんなことやっていきましたが、その真ん中には必ず「お客さまに喜んでもらいたい」という思いがあった、それはファンケルの原点です。
それがいつしか事業を伸ばすことだけに注力してしまい、大企業病になりかけてしまった。ファンケルが本来持っている「お客さまに喜んでもらいたい」という原点に立ち返り、お客様の体験価値はどこにあるのか、なぜファンケルを好きになってくれるのかということを可視化すれば、もっと的確にアプローチすることができるはずです。
それを実現するのは情報を扱う情報システム部門であり、それこそが情報システム部門の本来の仕事だと考えています。