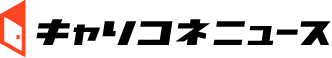主人公は、大手家電メーカーに勤務する羽嶋賢児、独身で実家暮らしの31歳。子どもの頃から科学オタクで、仕事のストレスは自宅で科学系のネット動画や生中継を見て解消している。友人はおらず、休日は科学シンポジウムに出席するのが楽しみという青年だ。
賢児は、この世にはびこる「似非(えせ)科学」、つまり科学的根拠がないのに、いかにも科学で証明された効能があるかのように謳う製品や情報に対して、強い憎悪・嫌悪を抱いている。それは彼の家族を含めた生い立ちが関係しているのだが、根底にはやはり「科学への希望と信頼」があるからだろう。
それだけに、科学リテラシーの乏しい姉や母親を見下すような言動が多く、家族との関係はギスギスしている。正直、読者から見てもあまり好感度の高い人物とは言えない。確かに賢児の主張は正論なのだが、人間正論ばかりで生きてはいない。正しいことを押し通そうとすればするほど、軋轢も多くなるものだ。
そこで「マイナスイオン」である。彼の勤務する会社はマイナスイオンが髪を美しくすると謳うドライヤーなどの美容家電が利益の柱になっている。しかし賢児にいわせれば、マイナスイオンなんてものは存在しないし、科学的根拠も効果もない。お客の美しくなりたいという願望につけ込んだインチキ商売だ。
年収600万円の転職組であり、他部署で実績を上げた賢児だったが、マイナスイオンの商品群を「廃止すべき」と上司に進言したことから、なぜか美容家電の開発部門に飛ばされてしまう。
姉は「母乳育児」を信じ迷走、根底にあるものは
賢児は自分の主義に反することを、ビジネスと割り切る必要があった。組織に属する社会人にはよくあることだ。だが彼は、どうしても「科学」への信頼を裏切ることができない。頭は良いはずなのに、そこは非常に不器用だ。誠実であろうとすればするほど周囲に否定されていく様子はつらく、
「私はただ……誠実でありたいだけです」
科学に、と言おうとしたが、声にならなかった。
という一文が胸に突き刺さる。最初は主人公をあまり好きでなかった筆者も共感や憐みを禁じ得ず、応援したい気持ちになっていった。
他方、賢児の姉・美空は初めての出産で「帝王切開では母性が育たない」とか「母乳じゃないと弱い子になる」といった言葉を信じ迷走する。「似非科学」が人を幸福にも不幸にもする様がこれでもかと描かれ、私たちの生活は意外なほど不確かな情報に取り巻かれていることに気付かされる。
しかし、本書の主旨は似非科学への糾弾ではないだろう。美容家電に誇りを持っている同僚の存在からも、それはうかがえる。問題は、私たちの精神的な弱さや科学リテラシーの低さだと思い至るのだ。
社会問題を描きながら、「科学とは何か」を問うてくる一冊
賢児には、科学者になった蓼科譲という唯一の親友がいる。彼の存在は大きく、譲こそが賢児が信じる科学の希望の星のようなものだった。ところが、譲を通して日本の若い科学者たちが置かれる苦境や、研究現場の危機的な状況が伝えられる。譲の発した「科学にもっともらしい効能をくっつけて売るようになってる」という言葉は、科学を信じる者にとって、どこまでも切ない。
だが本書は、辛い状況を描きつつも重くなりすぎず、どこかに希望を感じ読後感はさわやかだ。それは、作者・朱野帰子さんの科学への深い敬愛があるからだろう。がんの代替え治療や母乳育児を強いる弊害、ポスドクの不遇など、社会問題の数々を取り上げ、リアリティのある力強さで「科学とは何か」を問いかけてくる。
厳しい現実のなかで、賢児はどのような道を選ぶのか。科学好きのみならず引き込まれていく本書。好きなことを仕事にするのは難しい、けれど自分に恥じるような仕事はしたくない、というすべての働く大人たちにお薦めしたい一冊だ。