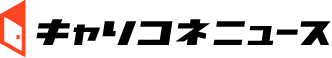石戸諭氏
コロナ禍でのオリンピックという異常事態に見舞われた東京で暮らす人たちの姿を描いた『東京ルポルタージュ 疫病とオリンピックの街で』(毎日新聞出版)。
インタビュー後半では、筆者のノンフィクションライター石戸諭に、「夜の街」を取材して歩いた理由を聞いた(聞き手:渡辺一樹/インタビュー前半は関連記事参照)。
クローズアップされた「夜の街」
――「都市で生活している人たち」を描こうとした理由は?
新聞とかテレビは、行政とか医療現場とか五輪組織委とかの取材が大変で、そこに大量の人員リソースを注ぎ込んでいた。そうなると当然、街のカバーは薄くなる。国や地方トップの方針が揺れる中、彼らが発する言葉によって、街がどんな風に振り回されていたかはとても重要なことなんだけど、いかんせん地味だし、追いかける人は少なかったように思う。
――じゃあ、歌舞伎町とか、新宿2丁目とかの話題が多いのは……。
そこがクローズアップされたエリアだったから。小池百合子都知事も「夜の街でコロナが〜」と繰り返していた。だから、そこで名指しした人たちに話を聞かなきゃいけないって思った。そして、取材に行ってみたら、そこでは、ものすごく前向きに頑張っている人たちがいた。
2020年夏の第二波で新宿区長や保健所がとった方針は極めて正しく、彼らは歌舞伎町の人達を上から押さえつけようとしなかった。そうではなく、ホストクラブを経営する歌舞伎町商店街振興組合・常任理事の手塚マキさんに連絡して教えを請い、歩み寄った。
歌舞伎町を職場とする少ない人たちも、貼られてしまったレッテルは払拭したいという思いはあった。だから、新宿区や保健所とも協力しながら、現実的な策を作り上げた。じわじわと理解者の和は広がって、検査もやって、ホットラインも作ってと、地道だけど着実な感染症対策ができあがっていった。
敵視して押さえつけるんじゃなくて、職場とする人を巻き込んで、協力者を増やし、包摂して対策をすると、感染症に強い街ができる。だから、もう歌舞伎町で感染者が激増したなんて話は聞こえてこないでしょ。
――聞かない。
もちろん完璧なんてありえないけど、大枠でいえば、対策が機能したってことだと思う。
現場には「自分たちの生活を守るんだ」っていう決意があった。自分たちが生きてきた街を大事に守ろうとする気概もあった。行政も保健所も彼らに対して敬意を払っていく。そうした連携の先にしか「感染症に強い街」はできないと僕は学んだ。
逆に、名指しして攻撃し、封鎖しろとか強い言葉で攻撃しても、感染症に弱い社会しかできあがらない。
――もっと感染が激増していたら、違うやり方もあるんだろうけど。少なくとも「生活を守る」っていうなら、夜の街で生きている人たちの生活も含めて考えないとおかしいよね。
実際にお金の部分、生活の部分を度外視して語っても現実は動かない。そこで生活する人達の生き方を否定しちゃったらダメですよ。誰も協力できなくなる。
そういう思いもあって、最後の方に神保町のバーの話を書いたんだ。緊急事態宣言は何カ月も続いたけど、それでも「ほとんどの店」は都の指示に従っていた。そのバーも緊急事態宣言に従って店を長期間閉めた。長期に渡って店を閉めることになっても、十分とは言えない補償の範囲内でなんとか持ちこたえていた店が無数にあった。
閉店を余儀なくされる店が次々と出てくる中、店側だって喜んで従っていたわけではない。でも、店側がなぜ従ったか、どういう思いで従っていたのかは、あんまり世の中に伝わっていない。
指示に従って休業・時短に協力した人達は、いろんな考えのもと、難しい選択を重ねて、その結論に至った。でもこうした努力、営業の姿勢があったことは、すっかり忘れられている。無数の、そして無名の協力者の存在が専門家もびっくりするような第5波「激減」という結果を出したのだと思う。
彼らにも仕事に対するプライド、誇りがあって、できる範囲で努力もしていた。なのに、なぜ一方的に悪者にされてしまったのか。こういった現実も書き留めておきたかった。
「コロナ禍でのオリパラ」東京の空気感を「真空パック」に
――この本を読んでいて、「ひょこっと訪れた部外者が第三者的な視点から好き勝手に書く」っていうことの大事さを、改めて感じた。ルポライターって無責任な存在だよね。話を聞く相手の生活に、責任を取れるわけでもないし。
そういう利害関係のない人が見たときに、どう見えるかは案外大事なんですよ。世の中には第三者が必要な場面がある。弁護士や裁判所のような揉め事の仲裁や当事者の代理という仕事、相談を受けるカウンセラーとか、当人とは無関係な人だからこそ、できること、聞けることがある。
自分たちのやってきた仕事、打ち込んできたモノを、急に「不要不急だ」と言われて、「自分たちのやってきたことって一体なんだったんだろう」と思い悩んでいた人は多かったんですよ。今も多いかもしれない。僕はそういう人たちを訪ねて、話を聞きながら描くことで、世の中にちょっと違った角度からの視点を提供できたらいいなと思っている。
歴史に残るコロナ禍、繰り返される流行の中で、東京オリンピック・パラリンピックがあって……。2020〜2021年は、いろんな人がいろんな場面で、悩みを抱えていたと思うんだよね。
『東京ルポルタージュ』にも登場する車いすのダンサー・神原健太さんは、パラリンピック開会式に自分が本当に出演していいのかどうかを、直前まで悩みに悩んでいた。自国開催のパラリンピック、おそらく一生に一度の晴れ舞台を、彼がどんな気持で迎えなければいけなかったのかを、多くの人は知らない。
――反対論も根強かったからなあ。しかし、オリパラもついこのあいだ終わったばかりなのに、もうみんなの記憶からは薄れつつある。あの時、語られていた話の多くは、すでに世の中から失われてしまったかも。
辻村深月さんとの対談でも話したのだけど、この本では、上手に「時代の空気をパッケージ」できたんじゃないかなと思う。
今回は書籍化でかなり加筆・修正したけど、もとが「週刊誌の連載」だったから、掲載時の時事的な話や、空気感が自然と話に織り込まれているんだよね。それを「真空パック」にして放り込んでいるような感じで、かなり時間が経過したあとに読んでも「当時の東京って、こんな空気だったんだ」と感じてもらえると思う。
――医療や政治の話は、大手の報道機関が手厚く報じてくれてるけど、ニュースだと街の空気感まではなかなか難しい。この本の記録は時間が経つほど、貴重になっていくのかもね。
あのとき何が起きていたか知らなかった、という人に読んで、「そうだったのか」と思ってもらえればいいな。
――ずっと都内にいても、歌舞伎町で何が起きていたかはわからなかった。自粛して過ごしていた人の多くがそうなのでは。
繰り返しになるけど、自分の生活圏外がどうなっているのか、想像する余裕もなかったですよ。でも、今回はいろんな場面を盛り込んだから、自分の友人・知人に近い人の話も出てくるかもしれない。
――リアルな場でつながっていた人たちの人間関係は、今回かなり分断されてしまっただろうね。
スパスパっと切られちゃって、かなり個別化してしまったと思う。人はつながりの中で生きているから、誰かの意見を聞いて自分の立ち位置を確かめたり、誰かに話を受け止めてもらったりすると、心が安定する。
――アニメが心の救いになったという話が出てきたけど、逆に「リアルでのつながり」に救われていた人もたくさんいる。それが切れたままになったら、かなり危うい。
そうだよね。同じ趣味の人がいるだけで救われるとか、場を共有できるだけで気持ちが楽になるとかいうこともある。
――映画館前の女性にしても、当時「鬼滅の刃」のことをリアルで語れる相手がいなかったのかもしれないよね。だから、面白がって、突然現れた謎の石戸氏を相手にいろいろ話してくれたのかも。
それは、あると思う。
――近所の飲食店に行っても、世間話とかできる雰囲気じゃなかったし。
どこも「会話を控えめに」だからね。
危機の時代、「分断」を煽る危うさ
ところで、ふと思い出した。政治学者のカール・シュミットによると、政治は究極的には「敵か、友か」を分割する。
――ん、何の話?
小池都知事が今回やったことは、それに合致していると思った。夜の街を「敵だ」と名指しすることによって、他をまとめる。危機の時代の政治は、そういうことをやりがちなんだよね。それもきちんと書き残したかった。
――なるほど。少数派を叩いて多数派の支持を得れば、自分の立場が安定するからか。
やっぱり、分断線を引いて、対立を煽るやり方はよくない。
ただでさえ、ライブハウスや劇場、飲み屋なんかの「不要不急」なものによるつながりが断ち切られて、不安定になってしまったのだから。今は、コロナ禍で失ったものを取り戻そうとしている途上なんだと思う
――そうだね。ただ現時点だと、それをどこまで取り戻して良いのか、わかりにくくない? 例えば、忘年会をやっていいか、とか。
そうだね。社会が元に戻るには、まだ時間がかかると思う。
だけど、「不要不急」と言われて追いやられたものが、往々にして人生に必要な「大切なもの」だということには、みんなも気づきはじめてるんじゃないかな。
「かわいそう。で話を終わらせたくない」
――それにしても、こんなにも長く緊急事態宣言とかマンボウが続くとは想像しなかった。
非常事態が起きると「あれもこれも制限」みたいになりがちだけど、「営業の自由」だってものすごく重要な話だから。どんな時に、どんな理由で自由を制限できるのかは、そんなに簡単な話じゃない。バランスがものすごく大事でしょ。
――単なるお金の問題だけではないもんね。人生かけてやってきた仕事が否定されたら、精神的にはかなりキツイ。ライブハウスでも劇場でも飲食店でも、リアルな「場」って文化も作り上げていたりする。
そういう場所を守れるかどうかって、結局、その場にいる人にかかっている部分も大きいんだよね。今回の本で僕がすごく大切にしていたポイントの一つが、登場人物が「大変だ」とか「かわいそう」とかで、話を終わらせないこと。
登場してくれた人たちはみんな、それぞれの危機を乗り越えようと試行錯誤していた。先行きが不透明で一寸先が見通せなくても、自分なりにできること、やれることを積み重ねていた。
今回の本で自分が描きたかったのは、東京で暮らす人達のそういう姿だった。そして、実践的な積み重ねの先にあるのが希望だと思っているんです。最後に希望が見えた、という感想が多く届いていて、僕にとってはそれが一番うれしいな。