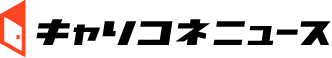写真:昼間たかし
「それでは入場できませんので、本日はお帰り下さい」
取材受付の列で少し前に並んでいた男性に、スタッフは気の毒そうに、しかしながら力強く告げた。感染拡大を防ぐためのあらゆる入場者へのチェックは極めて厳密だった。(取材・文:昼間たかし)
今までにない重苦しい影の中で感じる光明

写真:昼間たかし
12月30日、厳戒態勢の中でようやくコミックマーケットが再開した。今回の開催は99回目。次回は、いよいよ記念すべき100回目の開催である。東京五輪のため日程をずらして2020年5月の開催予定が中止になって以来、誰もが再開を待ち望んでいたコミックマーケット。そこには再開の喜びと同時に、ただならぬ緊張感が漂っていた。
一般参加者の入場はチケット購入かつ抽選制。ワクチン接種済み証明などの持参。会場内にも感染防止を呼びかける掲示があちこちになされ、消毒薬が設置されている。加えて、開催前の12月に入りオミクロン株の流行が再び世間を騒がせている。
感染せず、感染させず、かつ作品を頒布し、手に入れたい。そんな想いの錯綜が独特の緊張感を生み出していたのだ。
運営に携わる人たちに話を聞くと、強く伝わってくるのが「この場をつなぎとめたい」という思いだ。
たとえば「スタッフ」への配慮。コミックマーケットのスタッフはすべてがボランティアだ。集まった有志が協力しあい、仕事を分担し、独特の決まりが数多く存在するコミケという巨大なイベントを運営する。そこに積み上がったノウハウ、築かれた人間同士の繋がりも、長期間開催されないと、たとえ少しずつであっても薄れてしまう。
また本を頒布する人、購入する人たちのつながりも同様だ。たとえ、参加者数が制限され、厳戒態勢のもとでも開催し、継承していかなければならないものがある。会場には、そうした思いが確かに存在していた。
とはいえ、コミックマーケットならでは、ホッとする場面に一抹の光明も見た。それは、人との繋がりである。もともと参加者同士、あるいは描き手同士などなどいつもコミックマーケットで会うのが恒例という相手を誰もが持っているはずだ。
この2年間、SNSなどでやりとりはあっても、実際に顔を会わす機会のない人も多かった。久々に出会った相手は様々だった。2年間の間に随分と痩せた人、髪の毛がすっかりなくなった人。あるいは、増えた人などなど……。
そんな人々と再び出会い、軽口を交わす瞬間に「やっぱり来てよかったなあ」と思ったのである。
「それでも」人を惹き付けるコミケの魅力
ただ、例年取材してきた身からすると、「いつもとは違う」感覚があるのも事実だ。参加人数は制限され、本来ならいるべき人の姿が見えなかったりする。たとえば筆者が、コミケ精神を体現する作家のひとりだと感じているマンガ家エル・ボンデージ氏が今回、直前になってサークル参加を取りやめた。
かつては商業誌で作品を発表し、単行本を何冊も出したことがあるエル・ボンデージ氏だが、現在の作品発表の場は「コミックマーケット」だけ。本当ならば出たかったはず。
何があったかと心配になって電話をしてみると、氏は制作意欲を失っているわけではなかった。今も日々、机に向かってコツコツと描き続けているという。
不参加の理由は意外なところにあった。なんと「スマホを持っていないから入れないかも」と心配になっていたのだという。ええっ。コミケのサークル参加に、スマホは要らないですよ。
慌てて伝えたが、なにせスマホどころか、パソコンも携帯電話も持たず、電子メールを使ったこともないというエル・ボンデージ氏。サークル参加にメール登録が必須となったこともあり「どことなく疎外感を感じてしまった」というのだ。
そんな落とし穴があったとは。だが、そこは歴戦の猛者。完全に「心が折れた」わけではなかった。
「来年にはスマホを買おうと思って。今は週5で派遣の仕事に出ているんですよ。読者には申し訳ないと思っています。次回は必ず、しずかちゃんでも、ラムちゃんでもなんでもやりますから」
すでに氏は着々と「次」の参加計画を練っていたのであった。まさか氏にスマホ購入を決意させるとは……いやはや、コミケの魔力は底が知れない。これなら来年は、氏の元気なお姿を会場で見られることだろう。
また、あの開放感のあるコミックマーケットに戻るために、今しばらくは耐えることにしよう。